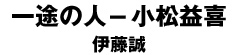昭和11年(1936)小磯は猪熊弦一郎、脇田和、佐藤敬らと新美術団体・新制作派協会を結成。小松さんも小磯の誘いを受けて二科会からこちらへ転じ、受賞を重ねて同会会員に。小松さんは今でも小磯、大塚の両氏に強い感謝の念を持っている。無名の画家を本当の意味での画家に育ててくれた大恩人はこの2人だ、と。
小松さんの作品に異人館以外のものが無いわけではない。しかしそれも異人館を描くのに差しさわりが起きた際、代理的にとり上げられてきたものが多いように見受けられる。
例えば戦争の激化につれ、建物を3軒以上連ねて描けば地図と見なされスパイ行為で検挙される(今では考えられないことだが)、それでなくとも外国人がらみの洋館は何かと妙な話題になり易かった。そんな状況にイヤ気がさして郊外の田舎家を対象にしたり、日本のふるさと奈良へ出かけて寺院と対したり(その奈良が結局小松さんの疎開先になってしまう)、それでも建物――一筋の信念は曲げなかった。
小松さんの密かな自負−−「私は戦争画を1枚も描いていない」
終戦と同時に小松さんは早々に神戸へ飛んで帰った。とりあえず家族は奈良へ残したまま。神戸は空襲で大被害を受け、残った異人館とて傷みを理由にいつ取り壊されるかも知れない。数少なくなった異人館を描き続け後世へ残すのが今や自分の使命だと決意、戦後の神戸の街をまたも自転車で走り回ることになったのである。
小松さんに私が初めてお会いしたのは、昭和26年(1951)晩秋のことだ。もっともこの時のことは小松さん側には覚えがないはずである。いわば一方的な“ご対面”。
11月上旬のある日、神戸市大倉山の市立図書館講堂で美術講演会が開かれ(近代美術館も市立博物館も、ましてや小磯記念美術館など無かった)、その講師の1人として小松さんが話をされたのである。私はその聴衆の中にいた。演題は「美術の味わい方」。
――この時私は地元新聞社の美術担当記者であった。といっても、やっと2ヵ月前に任命されたばかりの“駆け出し”。 実はこの昭和26年という年、いうまでもなく日本にとって重要な意味を持つ年だった。つまりアメリカ・サンフランシスコで講和条約が調印され、占領終結、独立回復。併せて20世紀後半開始の年。各界に出直し気分が横溢し、それなりの出来事が持たれた。美術の分野では大きいところで、2月「サロン・ド・メ東京展」開催。続いて春に「ピカソ展」、夏から秋にかけて「マチス展」来日(ともに東京に続いて大阪でも展観)。長い戦争と敗戦後の占領のため、いわば“第2の鎖国”を強いられていた日本の美術界へ本場フランスの現代美術群と現代の2巨匠の作品が一挙に押し寄せて来たのだから、美術家、愛好家は元より一般市民もかなり美術への関心を高めたのである。新米記者が講演会へ出向いたゆえん。