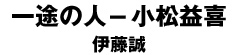ところで“青春”といえば、恩人・三木鶴久さんを介在とする妹ときさんとの出会いが、小松さんの人生にもう1つの希望の灯をともすことになった。ときさんは兄を頼って高知から上京、病母の面倒を見ながら働いていたのである。ときさんとは初対面ではない。高知市内でも同じ小学校区だから近所だったし、兄同士が親友で行き来もあり、小松さんより1歳下のときさんとはいわば顔なじみ。しかも偶然高知工業時代、校舎が向かい合わせの県立第一高女へ彼女も追っかけるようにして入学。男女交際に厳しい時代だけに親しく口をきくことは出来なかったが、思春期の小松さんは密かに思いを寄せていたという。束京での再会で当然彼女をしばしば訪れるようになり「マルクス主義を語り、未来を夢みて交友を深め」(つまり彼女を思想的にもリードして――)美校を卒業した年、2人は結婚した。小松さん25歳、ときさん23歳。
ただし結婚直前に一波乱あった。2人の間にではない。思想面で小松さんはやがて共産党に接触、卒業の年の2月、党中央幹部某氏をかくまった廉で渋谷署へ留置された。30日間の拘留。寒さがこたえたが、それよりも卒業制作の絵が未完である。このままだと留年決定。気が気でなく、放免になり飛んで帰ると、驚いたことに提出ずみになっている。密かに学友Kが未完の部分を補い一応完成させ届けてくれていた。
「学友はありがたいね。あの時のうれしさは未だに忘れられない」と小松さん。学校側は知ってか知らないでか(もちろん留置の報は届いていたはず)何の沙汰もなく、無事卒業。
ただ世間はそうはいかなかった。就職先ゼロ。アルバイトの稼ぎと、やがて結婚による夫人の収入を合わせて何とか、絵と主義2本立ての勉強という生活ペースを椎持する。秋の二科展に初応募して入選したものの、作品は6号P(40.9×27.3cm)という全出品作中最小作。到底大作を出せる状態ではなかった。
この頃ときさんもがんばっている。同盟機関誌「新美術」にドイツ語の評論「リベラ」を翻訳、掲載した。小松さんの僚友・佐藤敬のすすめによったものだが、メキシコの革命画家リベラの紹介は「もしかすると日本では最初だったかも知れません」――ときさんのちょっとしたご自慢である。「辞書を片手に大変でした」…画家の妻にふさわしいファイトといえようか。が、またも難事が…。やがてときさんは勤務先の会社での組合活動が抵触してクビになり、収入の道が無くなったのである。深刻な不況の時代であり、各地で労働争議も勃発。小松さんは覚悟して絵筆を折り共産党機関紙「赤旗」印刷の仕事に参加。しかし慣れない仕事のためか極度の緊張と疲労で遂にダウン。9日間の昏睡状態の後にやってきたのが記憶喪失症。友人、知人の顔がいっさい分らず、憶えていたのは夫人の面影のみ。しばらく療養に努めたが東京では病状が一一向によくならず、ときさんが付き添いふるさと高知へ引き揚げることになった。